出産が終わり、かわいい赤ちゃんがねんねしているのを眺めるのは、幸せなひと時ですよね・・・。

でも、産まれたばかりの赤ちゃんは、笑ってくれないし、毎日の育児に追われ、やりたいこともできないまま日々が過ぎて・・・、みたいなことになりがちです。
そんな育児が少しでも楽しくなり、赤ちゃんの自己肯定感が上がる「遊び方」について、お話します。
赤ちゃんの頃から「自己肯定感」を気にすべきか?
赤ちゃんはオムツを変えて、抱っこして、母乳やミルクをあげていれば、成長度合いは皆同じ、と思っていませんか?
もしかしたら、「自己肯定感を育むなんて、もっと先のことでしょう?」と思われるかもしれません。

もちろん、神経質にアレコレ悩む必要はありません。
でも、ママやパパが少し意識を変えるだけで、赤ちゃんの成長を大きくサポートしてあげられるのです。
その方法とは、『語り掛け育児』。
「自己肯定感」をサポートすると共に、「言葉」や「IQ(知能指数)」の発達も助け、後々の学校生活や成績にも影響することが分かっているんですよ。
私が実践したのは、こちらの本。
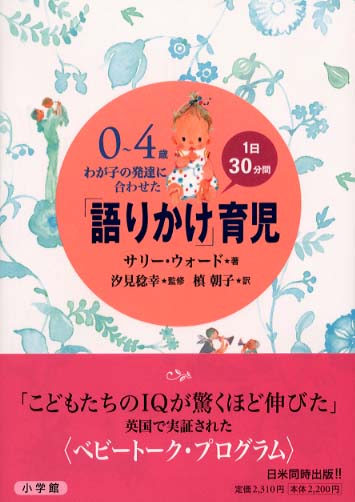
最近は、もう少し手軽に読めるバージョンも出ました。

「語り掛け育児」は、イギリスの言語聴覚士サリー・ウォードさんが、子どもの言葉の発達をサポートする目的で作られたメソッドです。
一体、どのような方法なのでしょうか?
赤ちゃんからできる「語り掛け育児」
「語り掛け育児」は、「産まれたて~4歳までの子ども」におススメの育児です。
やり方は、とっても簡単。「一日、30分、赤ちゃんに語り掛ける」だけ。
サリー・ウォードさんは、「ママやパパが家で楽しく実践できることが大切」と、おっしゃっています。
さて、「語り掛けるだけ」とはいっても注意すべきポイントがあります。
それは、雑音がなく、人の出入りなど、気が散る要素がない環境で、大人と赤ちゃんが、1対1で、心からしっかり向き合い、言葉をかけること。
その際、子どもに「反応してもらおう」「何か言葉を喋らせよう」と意図しないことが大切です。
語り掛けのルール
- 語り掛ける側の大人がリラックスして楽しんでいること、そのため自分の母国語で話しかけること。
- 「子どもの反応」を期待しないこと。
- 静かな場所で語り掛けること。
大人が、子どもに「していいことと、悪いこと」を教え、子どもは「大人の言うことを聞くべき」というのが、一般的な考え方かと思います。
それはそれでいいのですが、大人の要求や指示に従わされてばかりいる赤ちゃんや子どもは「自分の気持ちや、自分がやりたいことは、親にとって価値がない」と感じるようになっていきます。
その結果、もっと関心をもってほしくて、悪さをしたり、親の気をひくような言動をして、親にとって子育てがもっと大変になっていってしまいます。
反対に、「自分に大人が丁寧に反応してくれる」体験を繰り返した赤ちゃんは、「自分が感じていること」や「自分の言い分」があっていい、と感じるようになり、「自己肯定感」が上がるのです。
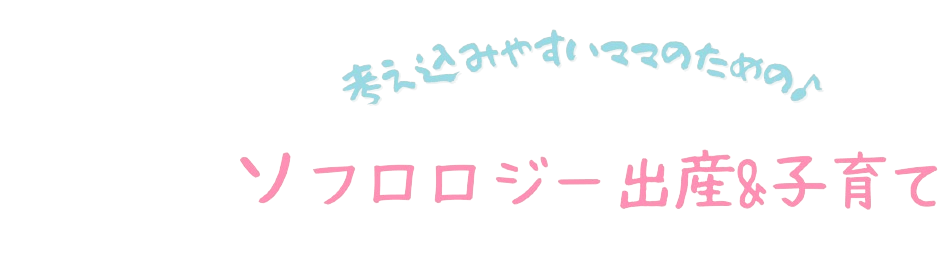



コメント