0歳児の赤ちゃんの寝かしつけに毎日ヘトヘト・・・。
そんな悩みがありませんか?
この記事では、そんなあなたの「寝かしつけ」が少しでも楽になる情報をお届けします。
私は「ジーナ式の寝かしつけ」を実践し、また、現在はセラピストとして活動しています。
自分の育児体験と、セラピストとしての知識を元に「ジーナ式育児の寝かしつけ」のコツについてお話していきますね。
このページの内容
ジーナ式育児 赤ちゃん一人寝する秘密
「ジーナ式育児」に限らず、赤ちゃんの眠りを育てるのに「育児スケジュール」を提案するメソッドは複数あります。
これって、当たり前のことなんです。
だって、睡眠というのは、生理的に体に必要なことなので、体の摂理を知らないと、「赤ちゃんを無理やり寝かせる」ことになり、赤ちゃんに「無理やり何かをさせる」のは、どう頑張ってもしんどくなっちゃうから・・・。
とはいえ、赤ちゃんがスーッと眠るには、「何がポイントなのか?」分かってないと、思わぬ落とし穴にハマっていることも!?
赤ちゃんが一人寝する3つの条件
「寝かしつけが楽になる」もっというと「赤ちゃんが一人寝する」には、次の3つが揃っている必要があります。
どんな音楽をかけるか、抱っこか、添い寝か、という『寝かしつけ技』を追求する前に、赤ちゃんの状況を整えることを考える方が先。
- 赤ちゃんが安心して満たされている。
- 赤ちゃんが「ここは寝る場所だ」「今から寝る時間だ」と思っている。
- 赤ちゃんが「眠たい」「寝たい」と思っている。
- 赤ちゃんが「眠た過ぎ」になっていない。
ジーナ式育児は「赤ちゃん一人寝条件」を満たすための智恵
「ジーナ式育児」というと、「スケジュール管理」が有名ですが、赤ちゃんのスケジュールを管理する理由は、赤ちゃんが「一人で寝つく力」がMAXになる、次の状態をつくり出すためなんです。
- 赤ちゃんが寝る時間に、赤ちゃんに満たされた状態になってもらう。
- 赤ちゃんが、程よく「眠たい」「寝たい」という状態になっているタイミングをバッチリ理解する。
「ジーナ式育児」が、どうやって、赤ちゃんが「満たされた安心した状態」を作り出しているかというと、何時頃お腹が空いて、何時頃眠くなる、という赤ちゃんのタイミングをママが先回りして準備することで、赤ちゃんが泣く前に満たしていってあげるんです。
実は、赤ちゃんは話すことはできませんが、「お腹が空いたサイン」「眠たいサイン」を出して、ママにアピールしています。
そして、「もう限界」というタイミングにきて泣くんです。
だから、「泣いたら授乳」「泣いたらねんね」という生活は、赤ちゃんからすると、いつも限界まで待たされている生活なんです。
それが毎度のことになると、今度は、「何か分かってもらうためには泣かなければ」と、『泣く – 要求を満たす』を結び付けて赤ちゃんに理解されることになります。
そうすると、些細な要求でも「大きな泣き声をあげる」⇒「お母さんがあやす」というコミュニケーションが定着します。
これが習慣化したまま「歯が生えてきて気持ち悪い」「イヤイヤ期でイライラする」となったとき、赤ちゃんは「お母さんがあやすもの」だと思っているので、育児がどんどん大変なものになっていってしまうんですね。
そこで、初めてのママでも、百戦錬磨の育児プロと同じ精度で赤ちゃんのサインを読み取れるようになってしまうのが「ジーナ式育児」のスケジュール。
この時間割りどおりに動いていれば、赤ちゃんは、泣いて訴える前に要求を満たしてもらえるので、「食べたい」と思ったときに出て来た母乳や哺乳瓶を食べればいい、「寝たい」と思ったときに寝ればいい、と思ってくれる子どもに育っていくわけです。
赤ちゃんの「一人寝が当たり前」の育児はらく
育児で過労になってしまうのは、「ママが何でもやってあげないとダメ」という状況だと思います。
食べ物をあげることは、どうしてもママが準備しないと難しいですが、「寝る」ことに関しては、赤ちゃんは「自分で寝る力」を持っています。
「自分で寝る力」はありますが、そのことに気づけるかどうか?は、大人の関わり方にかかっているんですね。
赤ちゃんは外の世界に産まれて来てから、ものすごい勢いで、自分がいる環境を理解していきます。
何が行われているかというと、色々な刺激を受けたときに「○○の刺激=△△という意味」という理解を積み上げていっているんですね。
例えば、「お母さんのにおい=安心」とか。
なので、「抱っこ=ねんね」とか「授乳=ねんね」という刷り込みが入ると、赤ちゃんに悪気はなくても「抱っこしてくれないから、寝ちゃダメ」と思って、起きていようと頑張ってしまうんです!(でも、眠たいから泣く・・・)
赤ちゃん一人寝の技
基本的に、慣れている場所、慣れているものに赤ちゃんは安心感を感じます。
なので、寝て起きた後に、授乳やミルクをあげて、その後遊んで疲れたら、そのまま一人で寝てくれるのが理想的。
そのために、「赤ちゃんの専用スペース(慣れている場所)」で遊んでもらって、そこでお昼寝もしてもらうのが最適だと思います。
「赤ちゃんの専用スペース」は、リビングの1区画を区切ってもいいし、ベビー布団でもいいと思います。
かわいくて、安心できる色のシーツなどで、そして夜に寝る場所と似たような環境が最適。(夜のお布団と同じ色柄、素材のシーツとかですね。)
赤ちゃんが、「ここは遊んでもいいし、寝てもいいし、自分が好きなように過ごしていい安心できる場所」という所を作れるといいですね。
寝かしつけを頑張り過ぎると・・・
赤ちゃんは、「○○=△△」という公式を理解をしている真っ最中。
このときに、ママが寝かしつけを頑張れば頑張るほど、「ママが頑張る=寝ても良い」という公式が出来上がってしまいます(泣)。
だけど、既に、これまで寝かしつけ頑張ってきたから、「抱っこ」「授乳」=「寝る」の公式ができちゃってるけど、それを変えたいママは、どうしたらいいのでしょう?
まずは、生活リズムを整えてください。
☆生後0・1・2ヵ月の赤ちゃんのスケジュールは、こちらの記事で。
☆生後3ヵ月~1歳の育児スケジュールはこちら。
〇 授乳量やミルクの量が足りているか、チェックしましょう。
〇 お腹の調子が気持ち悪くないか、チェックしましょう。
〇 他にも、何か赤ちゃんが満たされていないことがないか、観察してみましょう。
ここから、「寝かしつけ」を徐々に移行していく練習が必要になります。
元々、「抱っこ」や「授乳」で寝ていた赤ちゃんは、最初から、いきなり、それなしでは「寝ちゃいけないんでしょ?」という気持ちに赤ちゃんがなってしまうので、眠そうになってきたら最初は「抱っこ」などが必要になると思います。
でも、赤ちゃんが眠りに落ちるときには、一人でも寝られる場所で、睡眠に入るようにしてあげると「一人寝」への希望が見えてきます。
「抱っこして寝た」⇒「でも、お布団に置いたら、起きちゃった!」
これをなくす方法として、『横向き』で寝かせてあげると抱っこ中のまるまった姿勢がくずれないまま起きないよ、という動画をご紹介します。
この動画では、お母さんが赤ちゃんと密着している状態から、離れる瞬間を「徐々に徐々に、と、時間をとって行っています」。
そうなんです。
赤ちゃんって「温かさに安心感を感じる」んですね。(大人でもそうですけれども)
お布団に置かれると、「さむっ」ってなって起きちゃうんです。
コレの対策としては、スリーパーがあります。
スリーパーを着せて抱っこしておけば、スリーパーが温まっているので、赤ちゃんの体が直接冷たいお布団やベッドに触れない。
「寝かしつけ」を楽にするために
例え、「抱っこでねんね」や「授乳でねんね」の習慣がついていたとしても、生活リズムを気をつけて、授乳量やミルク量を整えてあげ、赤ちゃんが寝たいタイミングを逃さなければ、赤ちゃんの寝つきは良くなっていきます。
が、ガッチリ「抱っこ」や「授乳」にこだわっている赤ちゃんには、やはり、「ねんねの方法」を段階的に変えていく過渡期が必要だと思います。
個人的には、あまりにも苦労している場合、「明日から一気に、赤ちゃんを一人寝させるぞ~」をゴールにしない方がいいと思います。
そして、まずは、寝かしつけしているママが楽になり「育児の余裕ができる」ことを目標にするといいと思います。
何故かというと、ママが安心すると、赤ちゃんも安心しやすくなり、寝かしつけを含めた育児全体がスムーズにいきやすくなるからです。
というわけで、「寝かしつけ方法」の楽さをレベル分けしてみました。
赤ちゃん寝かしつけ楽ちんレベル
レベル1 赤ちゃんが一人寝してくれる。
レベル2 赤ちゃんが横たわっている状態で、ママが少しの間、傍にいれば寝ついてくれる。
レベル3 寝つくのに時間がかかるが、抱っこは必ずしも必要ない。
レベル4 「寝かしつけ」に抱っこが必須。(ベッドや布団に置くときに起きる可能性がある)
レベル5 抱っこでの「寝かしつけ」に長時間かかる。(ベッドや布団に置くと「寝かしつけ」が振り出しに戻る可能性がある)
レベル6 「寝かしつけ」は毎回へとへとになる上に、ベッドや布団に置いたら必ずすぐに赤ちゃんが起きる。
起きやすい赤ちゃんは、苦労して寝かしつけても、ちょっとしたきっかけで、また起きて「寝かしつけ」が振り出しに戻るので、本当に大変ですよね。
次に、長時間「抱っこ」しないと寝ない赤ちゃんも大変です。
どんな「寝かしつけ法」でも、短時間の寝かしつけで寝てくれたら、少し楽になります。
とはいえ、「抱っこ」で寝かしつけると、その後、ベッドへ下ろすときに「起きるかもしれないリスク」が常につきまといます。
というわけで、そのときは、多少、時間がかかっても、抱っこなしで「ベッドで寝てくれる」練習は、長期的にみてリターンが大きいんです。
寝てさえくれれば、「寝かしつけがリセットされる」ことがなくなる、ということと、眠りが浅くなったとき、ベッドの上で寝付くことが普通だと思っているので、すぐに泣いてママを呼ぶことがなくなるからです。
このことに気づいた私は「ベッドでのねんねレッスン」を始めました。
ベッドで寝かしつけ
とはいえ、突然、ママが思い立ったからといって、いきなり、赤ちゃんに「ベッドで寝なさい」オーラを出してもうまくいきません。
「今まで抱っこしてくれたのに~」と、赤ちゃんは意味が分からないからです。
ですから、「ベッドでねんねレッスン」を始めてすぐは、最初は、抱っこであやすを継続しました。
が、完全に寝入ってからベッドに置くのではなく、寝るか寝ないか「ウトウト状態」で、でも「赤ちゃん的には泣くより、眠いが勝っている状態」で、そぉっと、ベッドに置きました。
このタイミングを測るのが最初は大変ですが、一日の内に「寝かしつけ」は何度もありますから、何度も練習できます。
私も、最初は、赤ちゃんが起きちゃって「寝かしつけ」を1からやり直しも多かったのですが、だんだん、うまくいくことが出てきました。
「安定して、いつもうまくいく」状態には至らなかったのですが、だいぶベッドで「ウトウト状態」に慣れてきたように感じた頃、次の段階に移行しました。
次の段階とは、最初から抱っこはせずに、ベッドで赤ちゃんの隣に私がいるという安心感のレベルで寝てもらえるように練習したんです。
この時の「寝かしつけ」は、少しユニークで、赤ちゃんは最初からベッドで、隣で私が歌を歌う、というものです。
このときに歌う歌は、「子守歌」のような静かな物ではなく、赤ちゃんの泣き声に負けず劣らず元気で爽快なリズムのある歌でした(笑)。
私の娘は「穏やかな曲では寝ない子で」、抱っこやおんぶのときも、モーツァルトの交響曲38番のような軽快な曲で寝つく赤ちゃんだったんです。
そこで、リズム感のある選曲を子守歌にしました。
例えば、「ドレミの歌」「怪獣のバラード」などです。
⇓⇓⇓⇓⇓ 怪獣のバラード
寝かしつけの歌を歌うコツ
最初は、赤ちゃんの泣き声をかき消さんばかりに歌い、赤ちゃんの泣き声が弱まってくるのをみながら、歌声もだんだん小さくしていって、寝息をみながら、歌うのをやめる、という「寝かしつけ」
この「寝かしつけ」は、ロングヒットで、抱っこしなくてよくなったし、寝かしつけ時間も短縮できるようになり、「育児が楽になった」と感じた瞬間でした。
「ジーナ式育児」は、寝かしつけを含めた育児全般について、様々な智恵と事例が紹介されていますが、『寝かしつけ』に特化した智恵が満載されているのが「夜泣きドクター」麻里子先生の書籍です。
寝かしつけの技など、赤ちゃんとママの眠りに関する沢山の情報が掲載されている麻里子先生の本はコチラからご購入くださいね!
例えば、寝かしつけの智恵として、お昼寝ルーティーンなどが紹介されています。
例えば、楽しく遊んでいた赤ちゃんを、突然、寝る場所に連れて行って「寝なさい~」オーラを出しても、赤ちゃんはビックリしてしまいます。
そこで、まずはリラックスできるような内容の絵本を3分くらい読んであげて、「ねんね用のお友達(ぬいぐるみなど)」と一緒に、昼間に遊んだおもちゃ達や、お部屋に「おやすみなさい回り」をして(1分くらい)心の準備をしてあげて、その後、寝る場所に行って、子守歌を歌ってあげる。
様々なアイデアが、「赤ちゃんの睡眠研究」のデータと一緒に紹介されています。
特に、リケジョ・ママには、おススメですよ♪
赤ちゃんの一人寝は常識
実は、ヨーロッパの育児では「赤ちゃんが一人で寝られるようになる」ことは常識です。
だから、どんな大人も「赤ちゃんは一人で寝られるもの」と考えているんですね。
一方で、日本では「赤ちゃんは一人では寝られないもの」という考えの方が常識化していますよね?
大人が何を常識と考えているかは、赤ちゃんの「○○=△△」という公式が出来上がる過程で、とても大きな影響力があるんです。
なので、ママが寝かしつけにヘトヘト、イライラになるよりも、「赤ちゃんは寝るものよ~」と安心していることが大事。
とはいえ、頭で「大丈夫、大丈夫。この子は、もうすぐ寝る」と呪文のように唱えても、心臓がドキドキして、呼吸が乱れていると、やっぱり赤ちゃんは感じてしまいます。
そんな方におススメなのが、寝かしつけをしながら、ママが「腹式呼吸を行う」というものです。
赤ちゃんが愚図って「泣き止まない」、「寝てくれない」などのときに、実践してみてくださいね。
一人寝・育児の大失敗!【体験談】
私はフランスで育児をしていました。
娘は生後4ヵ月の頃から、週に二日だけ保育園に行くようになりました。
そして、保育園の先生から「一人で寝ることができるように、おうちでも練習してください」と言われるようになりました。
そこで、苦労しながら「一人ねんね」を練習し、だいぶ、できるようになった頃、娘がつかまり立ちができるようになりました。
そのタイミングで、危険を感じて私は、ベビーベッドの高さを床の位置まで下げたんですね。
すると、ママとの間に頑丈な柵が高々と立ちはだかり、閉じ込められた感が怖かったのか、娘が全く「一人ねんね」をしてくれなくなったんです。
それでも、数日、実施していたところ、娘の顔から、表情が完全に消えてしまいました!
遊んでいても、全然、にこりともしなくなりました。
もちろん、その後「寝かしつけ」の方針を変えるコトで、前のように表情豊かな娘に戻ってくれましたが。。。
娘が大きくなってから分かったのは、「周りの子に比べて、非常に感情が豊で、繊細な神経を持っている」という娘の特長です。
こんなに繊細な神経を持っているのに、他の子どもの基準に合わせて、「どんな環境でも一人寝ができるように」育児をしていたら、大変なことになっていたな、と今でも思います。
そして、手間はかかったけれども、娘に合わせた育児をしてきて「本当に良かった」と思っています。
発達特性 & 親の眠りの問題
育児書には、様々なノウハウが紹介されていて、共通の見解として「赤ちゃんは一人寝できる」「一人寝を練習してあげることは、赤ちゃんにとっても幸せなこと」というものがあります。
私もその通りだと思います。
だけれども、世の中には赤ちゃんでなくても「眠るのが苦手」な大人は沢山います。
そして、『赤ちゃんだから皆寝れる体質』なわけでもないと考えています。
例えば、私の夫は寝るのが苦手なんです。
疲れていても、すぐに寝つけない。
環境が変わると寝つけない。
変な寝方をすると、体が痛くなる。
眠くなってきて、脳が静まってくると、活動しているときには、活動に注意が集中して無視で来ていた「心の感覚」が湧き上がりやすくなります。
そういったもので脳が十分に静まらず、寝つきにくい特性の人は、どんな年齢の人でもいるのです。
赤ちゃんが、そういうタイプの子なのかどうか、というのは「親がどうか?」「親が子どもの頃どうだったか?」ということが、ある程度参考になるのではないかと個人的には思っています。
因みに、私も子どもの頃「寝ない子ども」で親が苦労していました。
つまり、わたしの家庭は、夫婦二人とも「寝ない子ども」だったんです。
そういった場合、自分の子どもが「一人で寝ようとしない」とか、「寝るのが嫌い・苦手」ということは普通な気がしていて(笑)、そういったケースでは、やはり『寝かしつけ』(隣で寝てあげる)などのサポートが必要な場合もあると思っています。
『赤ちゃんが一人寝』しないのは、自分の育児が悪いのだろうか?
と、思わず、「赤ちゃんを観察して理解」しながら、ママと赤ちゃんが楽になる生活スタイルを見つ頂けたら嬉しいです☆
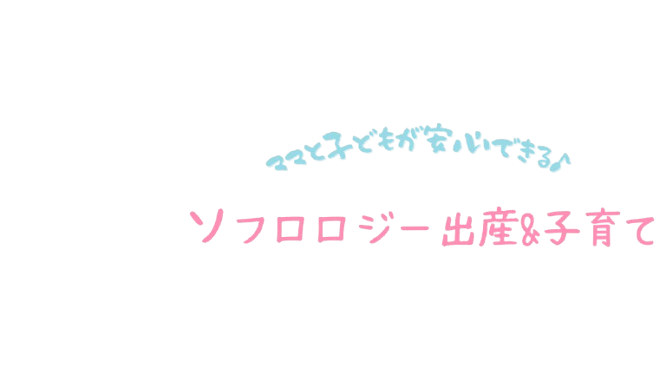



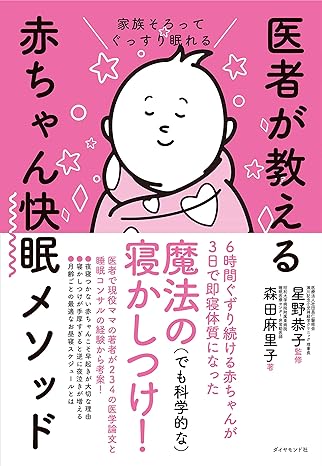
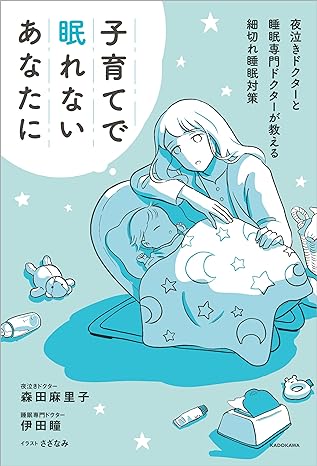
コメント