「新生児の赤ちゃんの子育てって何が一番大変???」
と聞かれると、ほとんどのママ・パパが「睡眠不足」と答えるほど、新生児育児の「睡眠」はストレスが溜まりがち。
あなたも新生児育児期の「睡眠不足」が出産不安の大きな原因になっていたり、今、将に「睡眠不足と闘っている」ということはありませんか?
この記事では、「生後0日~4週間の新生児」の睡眠の仕組みと攻略法について、お伝えしていきます。
このページの内容
新生児育児の睡眠リズムがママとパパのストレスになる理由
新生児育児の「睡眠」がママとパパにとって大きなストレス源になる理由、そのポイントは次の3つです。
新生児の睡眠がママのストレスになる3つのポイント
- 新生児は連続睡眠してくれない
- 新生児は起きやすい
- 新生児は寝る時間が決まっていない
新生児は連続睡眠してくれない
新生児は、何時間もまとまって一気に「寝る」ということができません。
産まれたばかりの赤ちゃんは、よく寝てくれる赤ちゃんでも4時間くらいが限界です。
ということは、必然的にママやパパも「4時間以上の連続睡眠がとれない」ということになるんです。
これは、しんどいですよね・・・。
新生児は起きやすい
新生児育児の赤ちゃんが寝てくれると、ホッとします。
ところが、「やっと寝た」と思った矢先、小さな物音や、ちょっとしたことで赤ちゃんは「すぐに起きて泣き出してしまう」性質をもっています。
特に寝かしつけにやっと成功したと思っても、「赤ちゃんの傍を離れる前に咳をしてしまったばっかりに、赤ちゃんを起こしてしまう」なんてことも。
赤ちゃんが寝ている間も、掃除機をかけたり、高い笑い声をあげたりするわけにはいきません。
赤ちゃんが寝ている間も、大人の生活の自由度は制限されてしまうんですよね。
(※赤ちゃんによって差があります。)
新生児は寝る時間が決まっていない
新生児の睡眠は浅く、「ウトウトしてはお腹が空いて起き、食べて少し遊んだら疲れてウトウトし始める」というサイクルが数時間ごとに繰り返されます。
そして、毎回「何時何分~何時何分まで寝てくれる」ということが正確には分かりません。
思ったより早く起きたり、よく寝てくれたり、まちまちなのです。
なので、必然的に新生児育児では、ママとパパが赤ちゃんの睡眠リズムに振り回される生活になってしまうんですよね。
このストレスから、できるだけ早く解放されるために、ママやパパにできることはあるのでしょうか?
その攻略法を探るために、「大人の睡眠リズム」がどのように調節されているのかを知っておきましょう。
新生児の睡眠攻略法
大人の睡眠メカニズム
大人は24時間を1サイクルとして睡眠と覚醒を繰り返すリズムを持っています。
この体内時計のことを「サーカディアンリズム(概日リズム)」と言います。
海外へ旅行したときに時差ボケを起こした経験はありませんか?
これは、日本の時計を元にした「サーカディアンリズム=体内時計」が、あなたの体内にあるからなんですね。
それでも、旅行先で数日~数週間もすれば、時差ボケも直りますよね?
旅行先の昼と夜のリズムに、あなたの「サーカディアンリズム=体内時計」が調整されるからなんです☆
どのようにして調整されているかというと、「光」や「観光や仕事への外出の時間帯」「食事」、「運動」などの刺激によって「活動的な昼」と「静かな夜」のリズムが調整されています。
このサーカディアンリズムに大きな影響を受けているのが「メラトニン」という眠気を起こす「睡眠」誘導ホルモンです。
睡眠障害がある方に処方される薬の中にも含まれていることが多いんですよ。
実は、このメラトニン分泌は、目の網膜から「光」が入ってくると、抑制される仕組みがあります。
「寝る前にスマホを見てはいけない、テレビを見てはいけない」と言われるのは、ここに理由があるんですね。
このように、大人の体内では「メラトニンというホルモン分泌が昼と夜の睡眠リズムを調節してくれています」が、生まれたての新生児には、まだ、このメラトニン量に昼夜の差がありません。
何故なら、胎児の頃は、ママの体内から分泌されるホルモンで赤ちゃんは生きていくことができたので、自分でホルモンを分泌する必要がなかったんですね。
特に、メラトニンに関しては、ママの体が分泌するメラトニンが胎盤を通して直接、胎児に影響を与えていると言われています。
生後は、いつからメラトニン分泌によって、サーカディアンリズムができてくるかというと、生後27日くらいからメラトニンの分泌に昼夜の差が出始め、生後3ヵ月になると、昼と夜のメラトニン分泌量にハッキリとした差がついてくるようになるそうです。
3ヵ月も、昼夜逆転になってしまったら、えらいことですよね・・・。
新生児の「睡眠」攻略法
新生児育児でママとパパが半泣きになるのは「赤ちゃんが昼夜逆転のリズムになってしまった」とき。
つまり、正しい昼と夜の時間帯で、サーカディアンリズムが安定してくれるだけでも、ママとパパの睡眠不足は解消されやすくなります。
そのためには、どんな方法があるのでしょうか?
「新生児の睡眠」-「妊婦時代の生活リズム」で攻略
先ほど、胎児はママのメラトニンの影響をダイレクトに受けているといいましたが、実際に、新生児の生活リズムは、妊婦さんの生活リズムと相関関係があると言われています。
つまり、「夜更かし型の生活を送っていた妊婦さんの赤ちゃん」と、「朝型の生活を送っていた妊婦さんの赤ちゃん」を比べたとき、「夜更かし型の妊婦さんの赤ちゃん」の方が、夜眠くなる時間が遅くなる、という傾向があるのです。
ということは、「産後は、赤ちゃんに、こういう生活リズムで過ごしてもらいたい」という昼夜のリズムで過ごすことを出産前から心がけることで、ある程度、新生児に昼と夜を教えてあげることができるということなんですね♪
新生児の睡眠攻略法 ~ 妊娠中の夜の過ごし方
- 室内の照明を薄暗くする
- テレビなどの騒がしい音を避ける
- 心拍や呼吸が落ち着き、血圧が落ち着くような環境を意識する
「新生児の睡眠」-新生児の「サーカディアンリズムの早期確立」で攻略
生れたばかりの新生児には、まだサーカディアンリズムが発達していません。
ただ、サーカディアンリズムの成熟を促す育児とそうでない育児はあります。
上手にサーカディアンリズムの成熟を促していきたいですね。
では、大人が海外旅行に行ったときのサーカディアンリズムが、どのような刺激によって調節されていたか、もう一度思い出してみましょう。
それは、「光」や「外出習慣」「食事」「運動」でした。
それでは、このような刺激によって体内のサーカディアンリズムを調節してみましょう。
サーカディアンリズムを育てる生活習慣
妊娠中
妊娠期から、体がしんどくても昼間は、できるだけ外へ出て光にあたったり、出産のための体力をつける運動をしたりすることで、胎児にも「活動する時間だよ」と教えてあげることができるでしょう。
光に当たることでホルモン分泌が調節され、活動することで心拍数や呼吸数、血圧が変化し、ママの心拍数と胎児の心拍数は連動していることが知られているからです。
つまり、ママが心拍数を上げて活動しているときは、胎児も心拍数が上がり活動状態になっているわけですね。
出産後
赤ちゃんが産まれた後も、昼間は、部屋の中に自然光を入れたり、外の風をいれたり、して新生児の5感を刺激する環境にしてあげ、夜は反対に、「暗く静かな環境」というように、昼と夜で環境のギャップを作ってあげると効果的です。
毎日、同じ時間帯に赤ちゃんにとって刺激的な活動をしてあげることで、新生児のサーカディアンリズムの成熟が早まることが分かっています。 (Wulff and Siegmund 2002).
刺激的な活動というのは、新生児のお遊びやベビー・マッサージなどのことです。
「授乳・ミルク」の時間でサーカディアンリズムを育てる
また、新生児の生活リズムは「授乳時間」にも大きな影響を受けます。
新生児期は、おっぱいを吸うことに疲れて「沿い乳」や「ミルク」で寝てしまう赤ちゃんが多く、それが「寝かしつけ」の方法として定着してしまうママは多いと思います。
ですが、実際には「睡眠」と「覚醒」の良いリズムが崩れてしまいやすくなります。
サーカディアンリズムを調節するための刺激の中に「食事」があったように、食事のあとは胃が活動します。
「胃の活動」は「良い睡眠を妨げる」活動なんですね。
胃が活発に活動している状態、お腹が張っている状態で、赤ちゃんが寝れば、胃がゴロゴロして覚醒したりしやすい状態になってしまうんです。
生れたばかりのときから、「睡眠」と「授乳・ミルク」を分けることで、あとあとの育児がぐっと楽になりますよ。
サーカディアンリズムを育てる新生児のスケジュール
昼と夜の活動に差をつけ、サーカディアンリズムを育てていくのに、色々なことを考えながら育児をするのは大変ですよね。
一人で、アレコレと考え過ぎなくても、このスケジュールを守れば「自然とサーカディアンリズムが育つ」という赤ちゃんスケジュールがあります。
※青い部分は「ねんね」の時間。

これらのスケジュールを提唱しているのは、森田麻里子先生と清水悦子先生。
森田麻里子先生は、お医者さんで、自身のお子さんが生後2ヵ月半のときに寝かしつけに苦労され、睡眠に関する医学研究を徹底調査して、メソッドを作られました。
(現在は、小児スリープコンサルタントの育成講座を開催していらっしゃいます。)
清水悦子先生も、元々は理学療法士さんで、長女さんの壮絶な夜泣きで育児ノイローゼになったご経験から生体リズムを主体にした夜泣き改善方法にたどり着き、本を出版されています。
このスケジュールに沿って生活を送ってみてください。
その際、「授乳・ミルク」は寝る直前ではなく、覚醒してから15分後にすることで、「睡眠」と「食事」を分けて赤ちゃんに覚えてもらうことができるようになります。
「起きて、お腹をいっぱいにして、遊びや活動」⇒「ねんね」⇒「起きて、お腹をいっぱいにして、遊びや活動」というサイクルを、毎日、同じ時間帯で繰り返すことによって、サーカディアンリズムが早く成熟してくれるようになるんです。
ママの睡眠不足を解消する方法
新生児の「夜のロング睡眠」攻略法
ママとパパが睡眠不足にならないための奥の手があるんです。
それは、ママやパパが就寝する時刻の前に、赤ちゃんに起きてもらい、いつもよりたくさんの授乳やミルクをしてあげ、赤ちゃんの就寝と同時に、ママとパパも一緒に就寝することです。
大人の睡眠は、最も深い眠りに入る最初の4、5時間が最も重要とされます。
その時間帯の睡眠が確保できるかできないか、だけでも、日中のスッキリ感が大きく変わるんですよね。
上記にご紹介したスケジュールでいくと、22時~23時の間の授乳が、一番いいかもしれません。
あなたの就寝前に、赤ちゃんにお腹いっぱいになってもらうことで、この大切な眠りを確保しやすくなります。
30分以内でママとパパもお昼寝
日中のパフォーマンスを上げる「睡眠法」の切り札といえば、「30分以内の昼寝」です。
この昼寝があるかないかで、午後のパフォーマンスに雲泥の差が現れます。
また、ソフロロジーの瞑想音声による20分の仮眠は、「夜の2時間の睡眠に匹敵する」という研究データが出ています。
リラクゼーション状態での仮眠ですから、体力の回復力も上がりますし、新生児期のママとパパには、ぜひ活用して頂きたい「睡眠不足解消の切り札」です。
ジーナ式育児
いかがでしたか?
色々やれることはありそうだと分かったけど「これらを上手に取り入れながら育児をしていくのも、大変なことだな~」と思われませんでしたか?
実は、麻里子先生や悦子先生だけでなく、他にも記事で紹介した内容が、きれいに盛り込まれた育児スケジュールがあるんです。
それは「ジーナ式育児」や「南アフリカ式」の育児。
「ジーナ式育児」は、イギリスのプロのベビーシッター(ナニー)ジーナさんが、300人以上の赤ちゃんをお世話してきた結果、見出した赤ちゃんにとって最適な生活リズムをメソッド化したもの。
そして、「南アフリカ式」の育児は、南アフリカの文化に溶け込んでいる赤ちゃんスケジュールなんです。
ジーナ式育児については、こちらの記事をご覧くださいね。
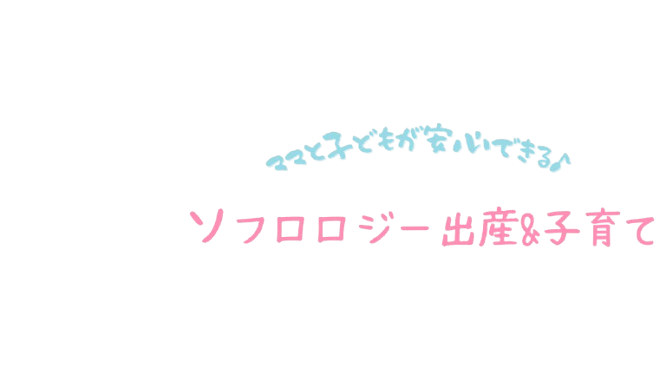




コメント